ベルトコンベアの温度監視
木片チップ・石炭が発火する前に、温度異常を見逃さない“接触式センサ”という選択肢

木片チップが燃えるのはなぜ?搬送ラインでの自然発火メカニズム
─ 蓄熱・摩擦・空気供給・粉塵の関係 ─
木片チップは一見すると安定した燃料素材ですが、搬送中の環境によっては自然発火のリスクを抱える非常に繊細な素材でもあります。特に、ベルトコンベアを使った大量搬送の現場では、「熱がこもる構造」や「粉塵の堆積」「摩擦熱の発生」など、発火を引き起こす複合的な条件が揃いやすいのが実態です。
ここでは、木片チップが搬送中に燃える理由を、現場でよく見られる4つの要素に分けて整理してみます。
■ 1)蓄熱:発酵や酸化による内部温度の上昇
木材やチップは、搬送前の保管中に微生物の活動や酸化反応によって“内部から熱を持つ”ことがあります。特に梅雨〜夏場にかけては、湿度と外気温が高いため、保管中に蓄積された熱が放散されないまま搬送工程に持ち込まれるケースが多く見られます。
さらに密閉気味の搬送構造(カバー付きのベルトなど)では、チップ間の熱がこもりやすく、外部からの冷却が不十分な状態でベルト上を移動することになります。
■ 2)摩擦熱:ベアリングやローラ部での異常発熱
搬送ラインにはベアリングや中間ローラなど、多くの可動部が存在します。これらの部品が劣化や潤滑不足によって摩擦抵抗を増すと、局所的に高温状態が発生します。
とくに古いラインでは、熱を検知する手段が限られていたり、摩耗に気づかないまま運転が継続されることもあります。その状態で可燃性の木片チップが接触または近接すると、“外部からの着火源”として機能してしまうリスクが高まります。
■ 3)空気供給:酸素があることで“燃えやすさ”が増す
搬送ラインは当然ながらオープンな構造が多く、酸素が常に供給される環境にあります。保管中の自然発火とは異なり、搬送中のチップは酸素との接触が多いため、一度温度が上がると燃焼が加速しやすいという特徴があります。
特に、チップが滞留するような箇所(詰まりや落下口など)では、酸素・熱・可燃物が一箇所に集まる「三要素」が揃いやすく、発火の引き金になります。
■ 4)粉塵:表面積が大きく、引火源になりやすい
チップの細かな粉塵は、軽く舞いやすい上に、発火点も低くなります。ローラや摩耗したベルト上、落下口の周囲に堆積した粉塵は、摩擦や火花で容易に着火します。さらに一度着火すると、燃焼速度が速く、ライン全体に広がりやすいのも特徴です。
搬送中は当然振動や風もあるため、粉塵が舞いやすい状況=拡散しやすい可燃源が常に存在しているとも言えます。
■ 小さな温度上昇が“最初のサイン”
発火に至るまでには、必ず「温度の異常上昇」というフェーズが存在します。言い換えれば、この温度変化を早期に検知し、対処できるかどうかが火災を未然に防ぐ分岐点になります。
だからこそ、“温度を監視できる仕組み”を搬送ラインに持たせることが、最も現実的かつ効果的な予防策になります。
次章では、その温度監視の手段として「どんなセンサが適しているのか」、特に「接触式か非接触か」の違いを整理していきます。

“ベルトコンベアが火元になる”のはどんなときか?
─ ベアリング劣化、詰まり、摩耗熱が“着火の火種”になる構造 ─
木片チップや石炭が火を吹く。そのきっかけは、いつも唐突に見えて、実は地続きの“熱”にあります。
その熱源として多いのが、ベルトコンベアまわりの“ちょっとした異常”です。
■ ベアリングの発熱は、静かに進む
ベルトを支えるローラーやプーリー。その中にあるベアリングは、少しずつ摩耗し、潤滑油が切れ、目には見えない発熱を始めます。
放っておけば、表面温度は100℃を超え、そのすぐそばにあった木片や石炭が、熱を蓄えて自然発火する。そんな構造が、実際の事故現場では繰り返されています。
機械は燃えません。ただ、燃えやすいもののすぐ隣に、高温の部品がある。それが問題なのです。
■ 詰まりや引っ掛かりが、火種を育てる
搬送中の木片が一部で引っかかる。石炭が落ちきれずに積もる。
そんな“よくあること”が、火災の入口になることもあります。
特に、ベルトが動き続ける中で、チップや石炭が詰まった場所では、摩擦熱がこもりやすい。
加えて、粉塵や細かな繊維が滞留することで、空気が溜まり、逃げ場を失った熱がじわじわと蓄積していきます。
気づいたときには「煙が出ていた」というケースも少なくありません。
■ 摩耗部が熱源になるケースも
さらに言えば、ベルトそのものや金属部品の“擦れ”も、長時間放置すれば発熱につながります。
もちろんそれ自体が発火するわけではありません。ただ、熱が出ていることに気づけなかった結果、可燃物に火が移る。
つまり、“熱を出してるもの”と“燃えるもの”が近すぎる。そこに問題があるわけです。
こうした環境では、「発火するのはあくまで木片チップや石炭」ですが、その直前に何が起きていたかを、温度でとらえる視点が求められます。
温度が上がっているのは異常のサインです。
火になる前に、そこを捕まえる。そうした予防設計の選択肢として、接触式の温度センサをどう活かすか。
その視点は、次章で触れていきます。

火災を防ぐには温度を見張れ
─ センサによる“予兆検知”の考え方 ─
木片チップや石炭が燃えるとき、その温度は一気に上がるように見えて、実際にはじわじわと熱をため込んでいることが多いです。
だからこそ、「温度を見る」ことが火災の予防になる。それも、“異常になる前”の変化をどう見つけるかがカギになります。
そこで使われるのが温度センサ。大きくは非接触式と接触式の2種類があって、どちらにも得意不得意があります。
■ 非接触式センサ:対象に触れずに温度を測れる
赤外線温度センサに代表されるのがこのタイプです。
機械や搬送物に直接触れずに、一定距離から表面温度を読み取れるのが特徴ですね。
・動いているもの(ベルトやワーク)に対して設置しやすい
・センサ自体が熱に触れないので、寿命が長い
・複数箇所を「面」で見るような使い方もできる
ただし、こんな注意点もあります。
・粉塵や水蒸気が多い環境では誤差が出やすい
・測定対象の表面状態(ツヤや色)で値がブレることもある
・設置位置がズレたり、対象が遮られたりすると計測できない
つまり、「広い面を、ざっくり見たい」なら得意だけど、対象が小さい/位置がブレる/粉塵が多いという条件下では、慎重な設計が必要になります。
■観測例
AIT(自己発火温度)
定義:外部の点火源(火種)が無くても、物質が空気中で自然に発火する最低温度。
例:ガソリンのAITは約 280°C → 火種がなくても、その温度以上で勝手に燃え出す。
液体や気体(溶剤・燃料)に適用されることが多い。
設備表面温度との関係
モーターやベアリング、コンベアの金属表面が AITやLITに近い温度まで上がると発火源になり得る
基準
・軸受(ベアリング): 50–90℃
通常は60°C以下、90°Cを超えると異常摩耗や潤滑不良の可能性が高くなる
・コンベアローラー表面 40–70℃
90°Cを超えると危険信号(摩擦等による影響)
しきい値例として
・90°C超 → 警報
・120°C超 → 緊急停止(設備停止)
接触式センサ:触れてこそ、正確にわかる

もうひとつが、対象物に直接触れて温度を測るタイプです。
熱電対や測温抵抗体などがこれに当たりますね。特にベアリングの温度監視には、接触式が多く使われています。
・対象の“芯温”に近いデータが取れる
・周囲環境に左右されにくく、安定した値が得やすい
・構造がシンプルで、メンテナンスや交換も比較的容易
設置には物理的な取り付けが必要ですが、それだけに「この部品が熱を持ち始めた」という確かなデータが取れるのが強みです。
■ どちらが正解?ではなく、“どう使うか”が大事
火災の予防という観点で考えると、
・広い面をざっくり監視するなら非接触式
・熱源になりうる部位を確実に押さえるなら接触式
といった役割分担が現実的です。
木片チップや石炭のように、自然発火のリスクが高い搬送物があるなら、
・ベアリング部、
・ベルトのテンション部、
・粉塵がたまりやすい箇所、などに
確実に“触れて測れる”センサを仕込んでおくことで、「気づいたら高温になっていた」を未然に防ぐことができます。

高温・粉塵・水に強い温度センサとは?
─ 搬送ラインで求められる条件 ─
「火災を未然に防ぐには温度を見張ることが重要」とはいっても、どんなセンサでも良いわけではありません。
特に木片チップや石炭を運ぶベルトコンベアのように、環境が過酷なラインでは、“現場でちゃんと使えるセンサ”じゃないと意味がありません。
ここでは、実際の搬送設備で必要とされる条件を3つの観点から整理してみます。
■ 設置性|センサは「取り付けて終わり」じゃない
搬送設備は常に動いていて、メンテナンスの余裕も限られています。
だから温度センサにも、次のような設置性が求められます。
・狭いすき間にも取り付けられるサイズ感
・ベアリングなどの発熱源に密着できる構造
・ライン停止せずに取り付け/交換ができる工夫
配線が複雑だったり、ネジ止めに時間がかかるものは、どうしても現場で敬遠されがちです。
「後から簡単に追加できる」「機械の構造にあわせやすい」設計が選ばれやすいポイントになります。
■ 耐環境性|壊れやすいセンサでは監視が続かない
次に重要なのが、環境への強さです。
木片チップや石炭を扱う現場では、
・粉塵が舞う
・ラインが高温になる
・散水・洗浄などで水がかかる
といった条件が日常的にあります。
ここで一般的な電子機器やセンサを入れると、すぐに故障してしまうこともあるんですよね。
そのため、選ぶべきは
・耐熱性(100℃〜150℃以上)
・防塵・防水構造(IP65〜IP67相当)
・配線や接点が腐食・断線しにくい設計
こういった要素を満たしたセンサが前提になります。
■ メンテ性|「監視しっぱなし」でこそ意味がある
どれだけ高性能なセンサでも、定期的に外さないと確認できない、センサ自体が消耗品で頻繁に交換が必要…
となると、導入した意味が薄れてしまいます。
搬送ラインは24時間動きっぱなしの現場も多いため、
・故障前に異常が検知できる信号出力
・モジュール単位で交換できる構造
・“設置し直さなくていい”長寿命設計
など、“放っておける安心感”があるセンサが現場では評価されます。
■ 過酷環境で“ちゃんと動く”を担保できるか
高温・粉塵・湿気が入り交じる現場では、「測れるかどうか」よりも、「何年測り続けられるか」が問われます。
そういう意味で、単にデータシート上の数値ではなく、現場での実績や使われ方まで確認して選ぶのが、安全管理の本質です。

まとめ|火災は“予兆”で止める時代へ
─ 異常温度を可視化できるかどうかが分岐点 ─
木片チップや石炭のような可燃性物質は、常に「火災リスク」と隣り合わせです。
ただ、何の前触れもなく突然燃え上がるわけではなく、そこには必ず“熱の兆候”があります。
たとえば──
・ベアリングの摩耗や詰まりで、いつもより熱を持っていた
・粉塵が堆積した場所の温度が、目立たず上がっていた
・設備の一部が高温になっていたが、誰も気づいていなかった
こうした温度の“違和感”を見逃さないことが、火災を未然に防ぐ最初の分かれ道になります。
逆にいえば、「温度を見張れるセンサがあるかどうか」で、事故が防げるかどうかが変わるということでもあります。
■ 非接触だけが正解ではない、“設置できるセンサ”という選択
最近では、光ファイバーやサーモグラフィといった非接触式センサも注目されています。
ただ、粉塵や蒸気、振動が多い環境では、思ったように温度が取れなかったり、定期的な清掃・キャリブレーションが必要になる場面もあるんですよね。
そういった現場では、「とにかく壊れず、しっかり温度が取れる」接触式センサの信頼性が改めて見直されています。
■ サンサーモは“温度を見張る”という仕事に強い
三陽電工が提供する「サンサーモ」は、まさにこの用途に向けて設計された接触式センサです。
・高温環境(最大200℃)でも常時監視が可能
・粉塵・水・振動に強い構造
・狭所・曲面・ベアリング周りにも取り付けやすい
といった特徴があり、搬送ラインや火災リスクのある工程でも多数の採用実績があります。
温度を見る。それだけのシンプルな仕事に、どこまで本気で取り組めるか。
それが、火災を防ぐための本質だと思っています。
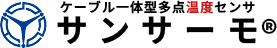
 お問い合わせ
お問い合わせ
